記事公開日
最終更新日
看護師が見た、スタッフが辞めない診療所の共通点
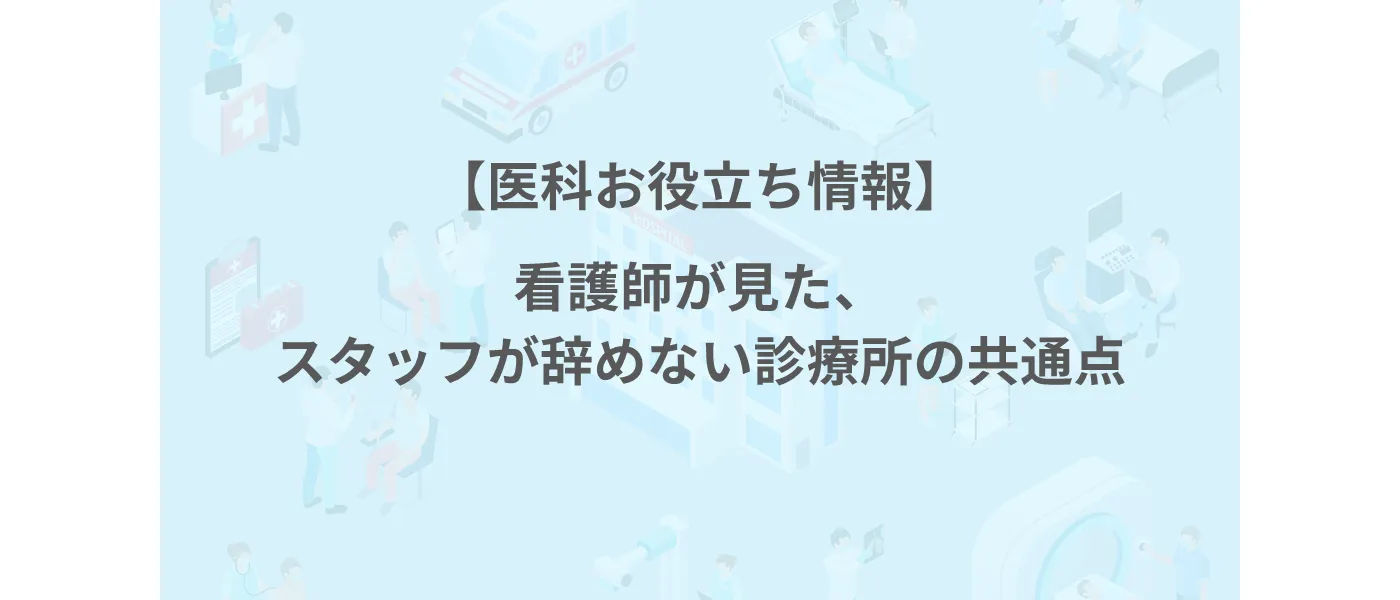
看護師として医療現場に携わる中で気づいたのは、スタッフが長く働き続ける職場には、目に見える明確な共通点があるということです。
電子カルテ導入をはじめとしたシステム整備がもたらす効果は、単なる業務効率化にとどまらず、職場全体の働きやすさを根本から変える力を持っています。
📝 \現場がまわる仕組み、できていますか?/
電子カルテ導入を成功させる“10の視点”をまとめました。
✔ 現場×経営の課題整理 ✔ スタッフ定着 ✔ スムーズな運用準備
📥 今すぐ無料ダウンロードする 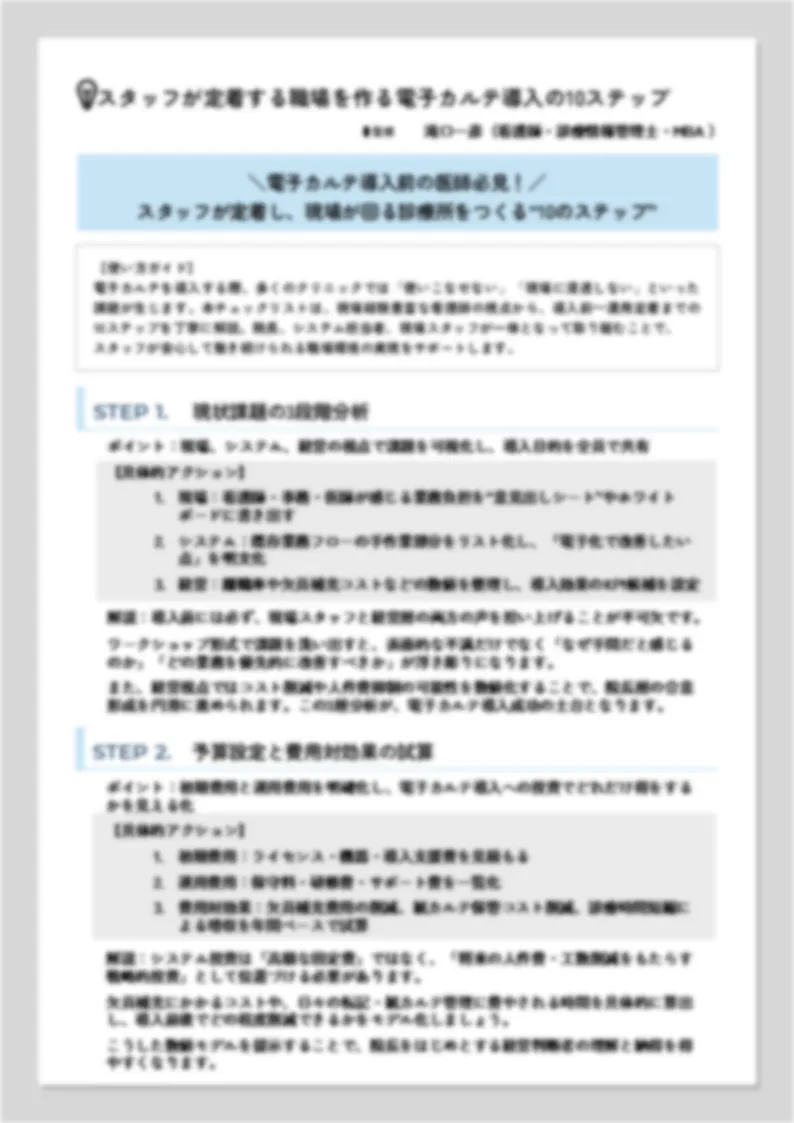
医療現場の人材不足が深刻化する中で
医療業界の人手不足は、もはや避けて通れない深刻な社会問題となっています。
厚生労働省の調査によると、医療・福祉業界の入職率は13.6%に対し、離職率は13.3%と、人材の確保と流出がほぼ同水準で推移している状況です。
(参考:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/kekka_gaiyo-02.pdf)
看護師の離職率について詳しく見ると、2022年度で11.8%となっており、新卒看護師では10.2%、既卒看護師では16.6%という数値が報告されています。
(参考:https://www.nurse.or.jp/home/assets/20240329_nl04.pdf)
全産業の平均離職率15.0%と比較すると看護師の離職率は決して高くありませんが、それでも「離職率が高い」と言われる背景には、医療現場特有の課題があります。
特に小規模なクリニックにおいては、一人のスタッフが離職した場合の影響は病院よりもはるかに深刻です。
欠員補充には時間と費用がかかり、その間は残されたスタッフへの負荷が増大します。
パーソル総合研究所の調査では、医療・福祉業界で2030年までに約49万人相当の人材が不足すると予測されており、この問題は今後さらに深刻化することが予想されます。
(参考:https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/assets/roudou2035.pdf#page=16)
このような状況下で、スタッフが長く働き続ける職場を作ることは、診療所経営における最重要課題の一つと言えるでしょう。
私が現場で見てきた経験から、スタッフ定着率の高い診療所には、必ずと言っていいほど共通する特徴があります。
共通点①:情報共有がスムーズな職場環境
スタッフが辞めない診療所で最も顕著に現れる特徴が、情報共有の円滑さです。
看護師として働く中で、「患者さんの情報が見つからない」「申し送りが正確に伝わっていない」といったコミュニケーションロスがどれほどストレスになるかを身をもって経験してきました。
電子カルテがもたらす情報の一元管理
電子カルテの導入は、このような情報共有の課題を根本的に解決します。
紙カルテでは、「カルテが見つからない」「他のスタッフが使用中で確認できない」といった物理的な制約が日常的に発生します。
これらの制約は、看護師や医療事務スタッフにとって大きなストレス要因となっていたのです。
電子カルテを導入すれば患者情報がリアルタイムで更新され、複数のスタッフが同時にアクセスできます。
診察室で医師が入力した情報は即座に看護師ステーションや受付で確認でき、処方内容や検査予定なども瞬時に共有されます。
ある医療機関の事例では、電子カルテ導入により「カルテを探す時間の削減」と「タイムリーな情報共有による患者様の待ち時間短縮」を実現しています。
このような効果は、スタッフの業務負担軽減に直結し、結果として職場環境の改善につながります。
チーム医療を支える情報基盤の構築
現代の医療は、医師、看護師、医療事務、薬剤師、検査技師など多職種の連携によって成り立っています。
電子カルテは、これらの職種間での情報共有を格段にスムーズにします。
例えば、看護師が測定したバイタルサインや検査技師が実施した検査結果は、即座にシステムに反映され、医師の診療判断に活用されます。
また、処方変更や治療方針の変更も、関係するすべてのスタッフに同時に伝達されるため、医療安全の向上にもつながります。
このような情報基盤が整備された職場では、「情報が伝わっていなかった」「確認不足によるミス」といった問題が劇的に減少します。
スタッフは本来の医療業務に集中でき、患者さんにより質の高いケアを提供できるようになるのです。
共通点②:業務負担の適切な分散
看護師として現場に立つ中で実感するのは、業務負荷の偏りがスタッフの疲弊と離職に直結するということです。
人手不足のクリニックでは、一人のスタッフが担当する業務量が多くなる傾向があり、これが「残業の日常化」「有給休暇の取得困難」といった問題を引き起こします。
電子カルテ導入による業務効率化の実現
電子カルテの導入は、スタッフの業務負担を大幅に軽減します。
従来の手作業や転記作業が自動化されることで、スタッフはより付加価値の高い業務に時間を使えるようになります。
具体的には、以下のような効果が期待できます:
- 診療記録の効率化:音声認識機能やテンプレート機能により、記録時間を短縮
- 処方箋発行の自動化:電子処方により、手書きの手間と転記ミスを削減
- 検査結果の自動取り込み:検査会社との連携により、手入力の必要がなくなる
- レセプト作成の自動化:診療報酬の自動計算により、事務作業を大幅に軽減
“誰でも使える”電子カルテは、定着と業務安定の土台です。

✔ ORCAとの連動で日常業務がスムーズに
✔ 誰でも迷わず使える直感的なUI設計
✔ 導入後も、専任担当が操作定着をしっかり支援
📩 今すぐ相談する(デモ申し込み・料金など)
属人化の解消と標準化の推進
電子カルテは、業務プロセスの標準化にも大きく貢献します。
紙カルテではスタッフごとに記録方法や業務手順が異なることが多く、これが属人化の原因となっていました。
電子カルテ導入により、入力フォーマットや業務フローが標準化されることで、誰でも同じ品質の業務を行えるようになります。
これは特に、新人スタッフの教育や休暇時の業務代替において大きなメリットとなります。
また、業務の見える化により、どのスタッフにどの程度の負荷がかかっているかを客観的に把握できるようになります。
これにより、適切な人員配置や業務分担の調整が可能となり、特定のスタッフに過度な負担が集中することを防げます。
共通点③:継続的な教育とサポート体制
看護師として多くの職場を経験する中で気づくのは、スタッフが安心して働き続けられる職場には、必ず充実した教育・サポート体制があるということです。
特に電子カルテなどの新しいシステムを導入する際には、この体制の充実度がスタッフの定着に大きな影響を与えます。
段階的な研修プログラムの重要性
電子カルテの導入において最も重要なのは、スタッフ全員が安心してシステムを使いこなせるようになることです。
一度に大量の機能を教え込むのではなく、基礎→応用→実践の段階的なアプローチが効果的です。
具体的な研修プログラムとしては:
- 基礎研修:基本操作の習得(1人1台での実習形式)
- 応用研修:実際の業務シナリオを想定したケーススタディ
- フォローアップ研修:運用開始後の疑問点や課題の解決
このような段階的な研修により、スタッフは無理なくシステムに慣れ親しむことができます。
特に、実際の患者ケースを想定した演習を行うことで、現場での応用力を身につけることができます。
研修が終了した後も、継続的なサポート体制を整備することが重要です。
電子カルテベンダーの多くは、導入後のサポート体制を充実させており、以下のようなサービスを提供しています:
- 操作方法に関する問い合わせ対応:電話やチャットでの迅速なサポート
- 定期的な訪問サポート:現場での使用状況確認と改善提案
- アップデート対応:法改正やシステム機能追加への対応
- トラブル対応:システム障害時の迅速な復旧支援
このようなサポート体制があることで、スタッフは安心してシステムを活用でき、業務に集中することができます。
院内でのナレッジ共有の仕組み
外部サポートだけでなく、院内でのナレッジ共有も重要です。
各部署から「電子カルテアンバサダー」を選出し、操作方法の相談窓口を設置することで、日常的な疑問や課題を迅速に解決できる体制を構築できます。
また、使い方のコツや便利な機能を院内で共有する「活用コミュニティ」を形成することで、スタッフ全体のスキル向上と満足度向上を図ることができます。
成功事例:定着率向上を実現したクリニックの取り組み
私が実際に見学させていただいたA診療所(内科・小児科)の事例をご紹介します。このクリニックは、電子カルテ導入を機にスタッフ定着率を大幅に改善することに成功しました。
導入前の課題
A診療所では、以下のような課題を抱えていました:
- 情報共有の非効率性:紙カルテのため、患者情報の共有に時間がかかる
- 業務負荷の集中:ベテランスタッフに業務が集中し、残業が常態化
- 教育体制の不備:新人スタッフへの指導が属人的で、定着率が低い
これらの課題により、3年間で看護師4名、医療事務3名が離職し、慢性的な人手不足に陥っていました。
電子カルテ導入と改善施策
院長は電子カルテ導入を決断し、同時に以下の施策を実施しました:
- 段階的導入計画:3ヶ月かけて基礎→応用→実践の研修を実施
- 業務フロー見直し:電子化に合わせて非効率な業務プロセスを改善
- サポート体制整備:各部署からリーダーを選出し、相談窓口を設置
- 定期的な振り返り:月1回のミーティングで課題と改善策を共有
導入後の効果
電子カルテ導入から1年後、以下のような効果が確認されました:
- 診療効率の向上:患者1人あたりの診療時間が平均15%短縮
- 残業時間の削減:月平均残業時間が30時間から12時間に減少
- スタッフ満足度の向上:年次アンケートで「働きやすさ」が4.2/5.0に改善
- 離職率の改善:導入後1年間の離職者は0名
特に印象的だったのは、スタッフの皆さんが口々に「情報共有がスムーズになった」「患者さんに集中できる時間が増えた」と話されていたことです。
技術的な効果だけでなく、働く環境そのものが改善されたことが、定着率向上の大きな要因となったのです。
継続的な改善への取り組み
A診療所では、導入完了後も継続的な改善に取り組んでいます。
四半期ごとに業務フローを見直し、新機能の活用や運用ルールの最適化を行っています。
また、地域の勉強会に参加して他院の事例を学び、自院の取り組みに活かしています。
このような継続的な改善姿勢が、スタッフの成長実感とモチベーション維持につながっており、「この職場で長く働きたい」という意識の醸成に寄与しています。
まとめ:システム投資は人材投資への第一歩
看護師として現場を見続けてきた経験から言えることとして、電子カルテをはじめとするシステム投資は、単なる「効率化のための道具」ではなく、「人材投資への第一歩」だということです。
医療現場では「患者の命を預かる」という重い責任を負いながら、日々多くの業務をこなさなければなりません。
非効率なツールや煩雑な手作業は、スタッフの疲弊を招き、最終的には離職という形で現れます。
欠員補充にはさらなる費用がかかるとも言われ、人材の流出は経営に深刻な影響を与えます。
一方で、適切なシステム投資により情報共有の効率化、業務負担の適正化、教育・サポート体制の充実を実現できれば、スタッフは安心して長く働き続けることができます。
これは結果として、継続的で質の高い医療サービスの提供につながり、患者満足度の向上と経営の安定化をもたらします。
導入や運用設計でお困りの際は、現場ごとのきめ細かいサポートが強みのZebra for Cloud-Karteまでお気軽にご相談ください。貴院のDX推進を全力でご支援いたします。
※この記事では、医療現場での実体験をもとに執筆していますが、個人情報保護の観点から具体的な医療機関名は仮名とし、詳細情報は匿名化して記載しています。
| 📝 スタッフが定着する電子カルテ導入の10ステップDL 10ステップ解説 × 現場向けアクションリスト付き 📥 無料で資料をダウンロードする 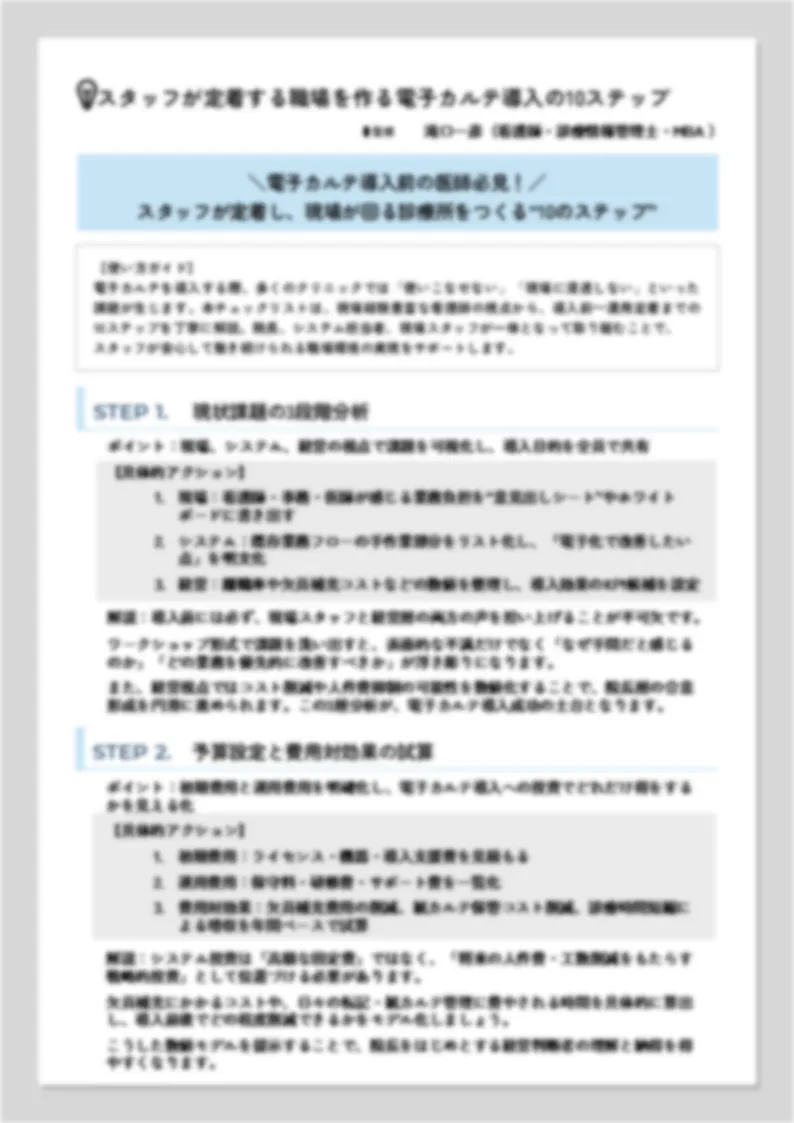 |
🏥 ORCA連携 × クラウド対応 × 定着支援体制

実際の画面・操作を専任担当がわかりやすくご案内します。
📩 今すぐ電子カルテ デモを申し込む
著者紹介
著者:滝口 一彦
看護師・診療情報管理士・MBA。医療現場での実務経験と経営視点をあわせ持つ医療系ライター。
大学病院・クリニックでの現場経験を活かし、電子カルテや業務効率化、スタッフ定着など、医療現場のリアルな課題に寄り添った記事執筆を得意とする。
noteでの執筆実績は300本以上。専門用語をやさしく解説し、現場目線と経営目線の両立を意識したコンテンツ制作を行う。
医療機関の現場力向上と、患者満足度・スタッフ満足度の両立を目指し、現場の声とデータに基づく提案を続けている。
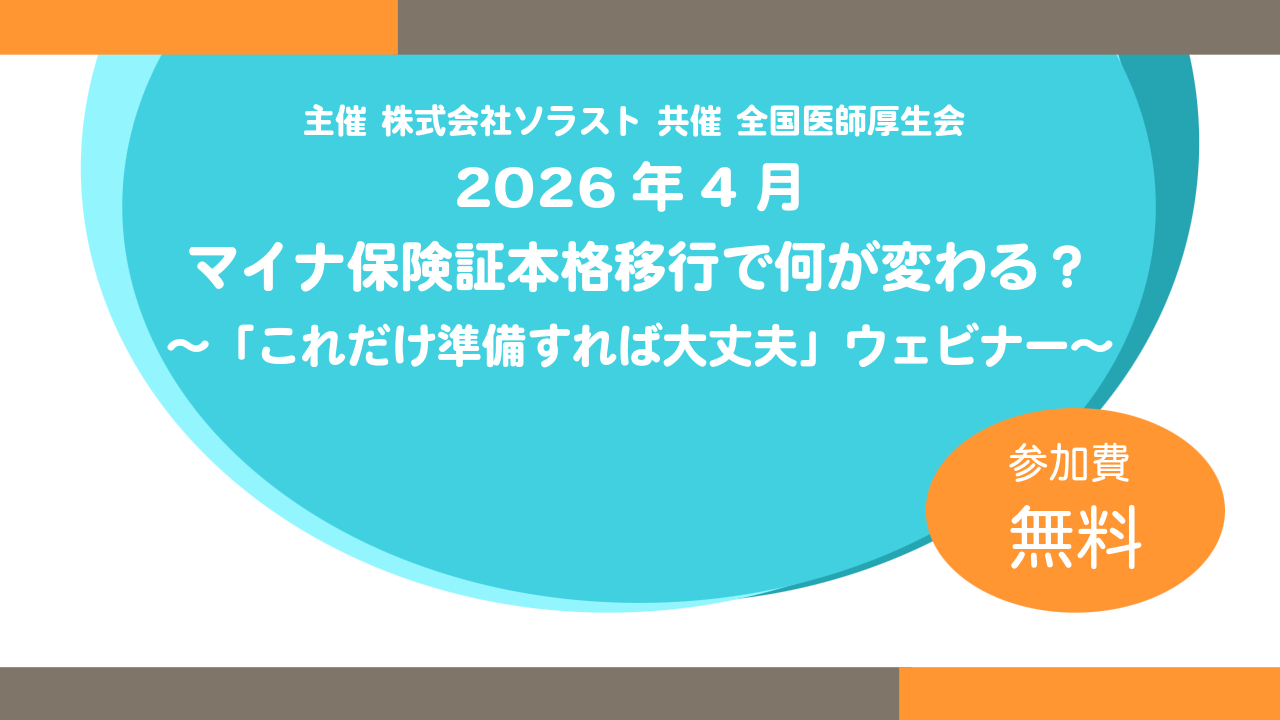
.pptx (1).webp)