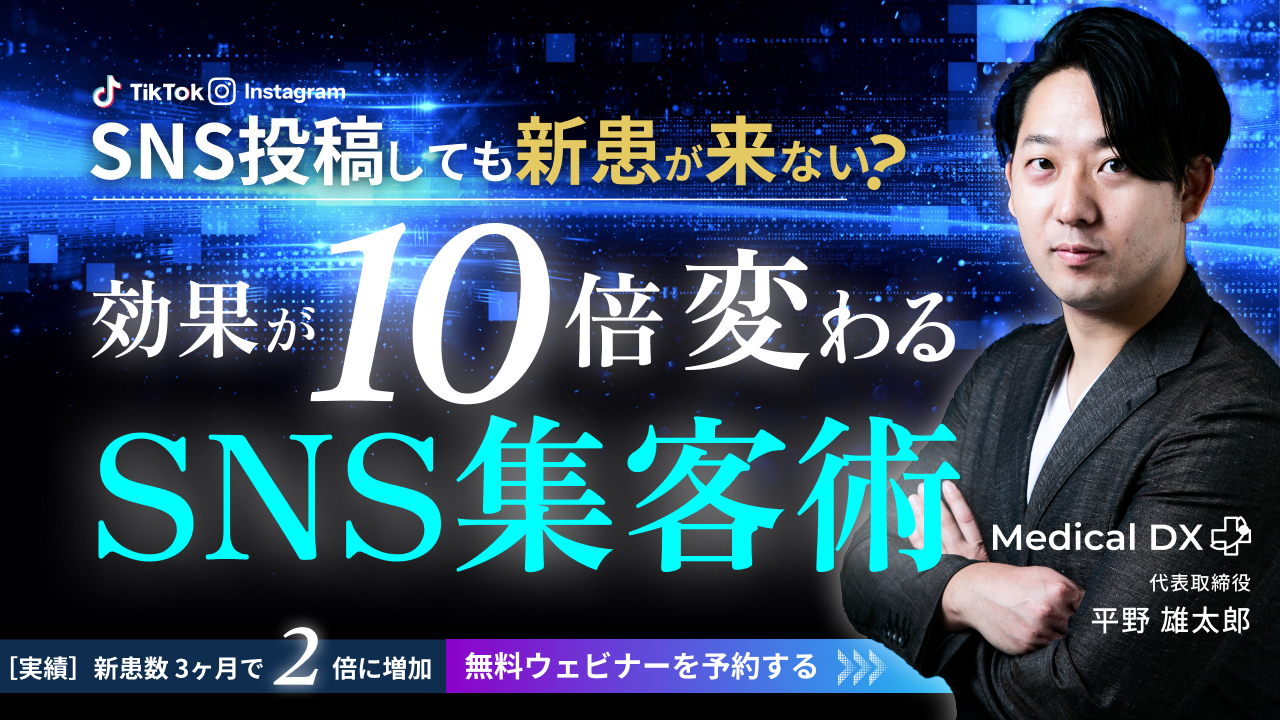記事公開日
最終更新日
毎日の診療にストレスフリーで、行政指導にも適切に対応するためのレセコン選定とは(新規開業編)

“最低限やるべきこと”をまとめた無料チェックリストをご用意しました。
- 患者指定前/後のToDo
- 掲示物・帳票の確認ポイント
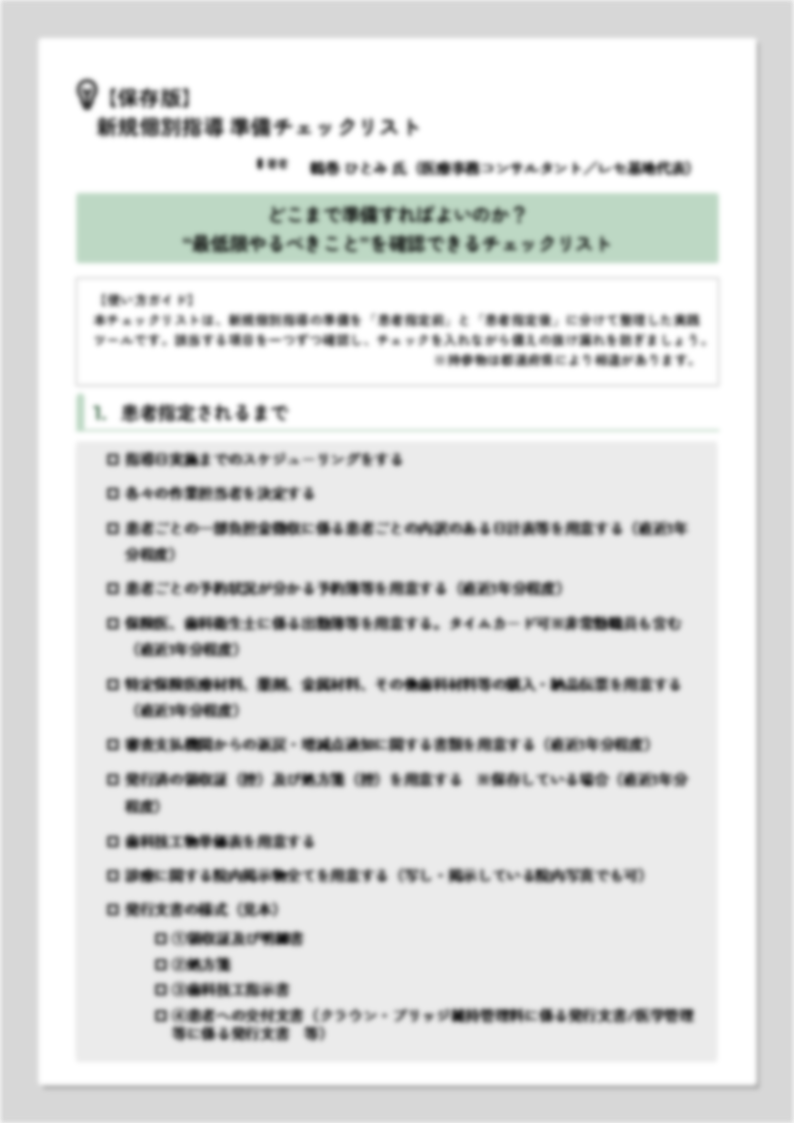
レセプトコンピューター(レセコン)と電子カルテ
現在は、原則として全ての医療機関でオンライン請求が義務付けられており、その普及率は99.2%に達しています。※社会保険診療報酬支払基金データ令和5年7月現在
まず整理したいのは現在ほとんどの歯科医療機関が導入しているのは「レセプトコンピューター(以下レセコン)」であり「電子カルテ」ではありません。
しかし今後、厚生労働省は2026年度までに電子カルテの普及率を80%に、2030年までには100%にすることを目指しています。
よってほとんどの医療機関は現在使用されているレセコンもいずれは電子カルテに移行しなければならないのです。
その時がきたら、今使用しているレセコンをそのまま使用し電子カルテ化するのか?または別のソフトに入れ替えるのか?歯科医療機関が選択するのはそう遠くはないのです。
現状
歯科医療機関における行政指導の失敗は様々な要因が考えられるが、その中のひとつの原因として医療機関が導入しているレセコンの機能にも原因がある場合があります。
特に新規開業の際には「学生時代に医局で使用していたから」「業者さんに勧められたから」「既に開業している友人が使用していたから」「安価だったから」などの理由で導入していると思います。
大学病院または勤務先で使用していたから
・これは一番に〝慣れている〟という理由で導入される医療機関が多くあります。
但し開業すると最終的に誤請求がないかどうか等の〝レセプト点検〟という作業が必須です。
大学病院では医事課、または勤務していた医療機関では管理者(院長)等が必ず点検をしています。その作業をご自身できちんとできるか否かが問題です。
業者さんに勧められたから
・開業時に機材等全てをお任せするメーカーでもレセコンをリリースしています。
当該メーカーのユニット・X線等とリンクするため導入する医療機関が多いのが現状です。先生のご希望される機能が積載されているレセコンであれば特に問題は出ません。
既に開業している友人が使用していたから
・既に開業されているご友人あるいは所属される団体から紹介され導入される場合もあります。ソフトによっては先生の意に沿わない操作をするソフトもあるため必ずメーカーに来てもらい実際の操作をデモンストレーションしてもらいましょう。
安価だったから
・あまりお勧めしません。高額なソフトはそれなりの機能が積載されています。逆に安価なソフトもそれなりの理由があります。例えばセキュリティに不安がある、機能が甘い、操作指導に来てくれない、マニュアルを見て先生方が入力を行わなければならない・・・等になります。
レセコンを選ぶ際のポイント
現在リリースされているレセコンは大きく2つのタイプがあります。
オンプレミスタイプとクラウドタイプです。
オンプレミスタイプは自院にサーバー(親機)を設置し運用します。セキュリティ管理がしやすくインターネット環境に依存しにくい特徴があります。
クラウドタイプとはインターネット環境を使用して運用します。メーカーによるシステムのバージョンアップやメンテナンスがしやすいのが特徴です。
ポイント①機能
・自院に必要な機能(レセプト作成、予約管理など)が積載されているか確認しましょう。
・エラーチェック機能が充実していることは重要です。誤入力をしてしまうと後日患者への返金または未収分回収作業が発生します。
・訪問診療を実施する医療機関は、介護保険の請求が標準搭載されているソフトが必須です。現在は、ほぼ全メーカーが標準搭載していますが一部オプション機能となっていたりするため必ず確認しましょう。
ポイント②操作性
・毎日の診療で使用します。カルテ入力がスムーズに行えるよう操作する側のニーズに合った〝使いやすさ〟を確認しましょう。
ポイント③セキュリティ
・入力されたデータは患者の個人情報です。セキュリティ対策は万全でなくてはなりません。
ポイント④コスト
・初期費用・月額費用・保守費用を考慮し予算に合ったものを選択しましょう。
・安価な場合はセキュリティに不安がある場合も多くあります。
ポイント⑤サポート体制
・リモートサポート(遠隔操作)、トラブル発生時の対応体制等、充実したサポート体制が整っているソフトを推奨します。
・災害時の対応も確認しておきましょう。
ポイント⑥サポートセンターが社内にあること
・ほとんどのメーカーがサポートセンターは設置しています。ここで推奨するサポートセンターは社内で対応しているという事です。
リモートワークの普及によりサポートセンターに連絡をしても個人の携帯に転送されている場合があります。
その場合、問い合わせした内容によっては即答できず折り返しの対応になりがちです。
先生がレセプトを作成する期間は定められていて、ぎりぎりで作業にあたる場合もあります。速やかに対応してくれるのは社内で対応している場合です。
社内には操作指導を行うインストラクターがおり操作に関して対応、ソフトの不具合はシステム担当者が原因を調査します。
社内にサポートセンターがあり社員が常駐しているという事はワンチームでサポートしてもらえるという安心に繋がります。
ポイント⑦バージョンアップ
・先に述べましたがレセコンにはオンプレミスタイプとクラウドタイプがあります。点数改定の際にはソフトのバージョンアップが必要です。
クラウドタイプはレセコンを起動した際に行われるため画面に表示されるボタンをクリックするだけで手間がかかりません。
現在はオンプレミスタイプも遠隔操作により再起動した時にバージョンアップをするよう組み込まれているものがほとんどですが、なかには媒体が送付されてきて医療機関で操作しなければならないメーカーもあります。
「CDをかけるだけでは?」と思いがちですが、サーバー(親機)だけではなく紐づくクライアントPC(子機)にもかけなければならない場合もあります。
また歯科用貴金属価格の随時改定が年4回あるため煩雑な作業かもしれません。
ポイント⑧導入実績を確認する
・導入を検討している場合は当該メーカーがどの程度のマーケットシェアを占めているのか導入実績を確認しましょう。少なくとも開業地の都道府県での導入実績は必要です。
診療報酬は2年に1回(金属改定含まず)、介護報酬は3年に1回、厚生労働省による点数改定があります。点数改定作業に対応するメーカー側の対応は簡単なものではなく煩雑で大変な作業です。トラブルも多く発生します。
大きな点数改定を少なくとも10回以上は対応しているメーカーを推奨します。これは実績と経験が伴っているため確認するポイントです。
行政指導の「新規個別指導からの再指導」は歯科医師の保険ルールの理解不足が原因で起こる事がほとんどですが、実際にはレセコンの誤操作、機能性が原因となったケースも少なくありません。
とくに「カルテの記載タイミング」や「印刷日」といった基本的な運用が、レセコンの仕様によって正しく管理できていないのが原因です。
導入実績が一定程度あるメーカーはこういった問題はクリアしていると考えてよいと思います。
「新規個別指導で再指導」となった事例
実際に、レセコンの機能や運用ルールへの理解不足から「新規個別指導で再指導」となったケースも発生しています。
とくに「カルテの記載タイミング」や「印刷日」といった基本的な運用が、レセコンの仕様によって正しく管理できていなかったことが原因です。
以下では、実際の指導事例とともに、どのような記載が“指摘対象”となり得るかをご紹介しています。
具体的な記載内容をご覧になるには、下記フォームよりご登録をお願いいたします。
| 📝 “知らなかった”を防ぐ、先生の味方になる1枚です。 科医療機関の実務を熟知した専門家監修の新規個別指導チェックリスト。 準備の道筋が見えることで、安心して当日を迎えられます。 📥 無料チェックリストをDLする 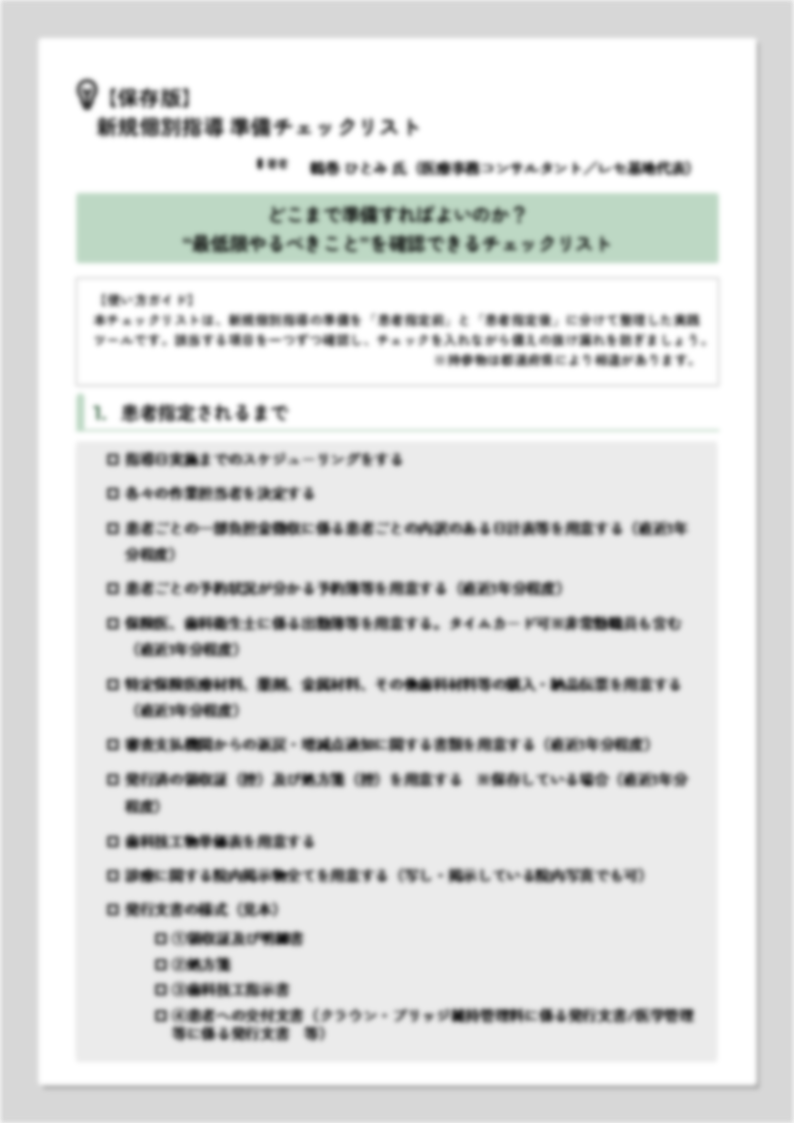 |
🦷 “スムーズなカルテ記載・オンライン請求自動化”できるレセコンをお探しなら
指導対策に直結する日々の業務を、スタッフ全員が“迷わず使える”操作性でサポート。![]()
Sunny-XROSSが、安心のスタートを後押しします。
📩 今すぐ相談する(導入の流れ・料金など)
著者紹介
著者:鶴巻 ひとみ (医療事務コンサルタント/レセ基地代表)
ソフトウェアメーカーを経て、歯科診療報酬の専門家としてキャリアを築く。これまで全国1,600件以上の歯科医療機関をサポートし、実務に基づいた豊富な経験と実績を持つ。
また、各地の歯科医師会、医療法人、歯科関連企業を対象に、診療報酬請求に関する研修会を多数実施。現場の課題に即した分かりやすい指導に定評がある。