記事公開日
最終更新日
職員が辞めたくなるクリニック、意外な“カルテの使い方”が原因かも
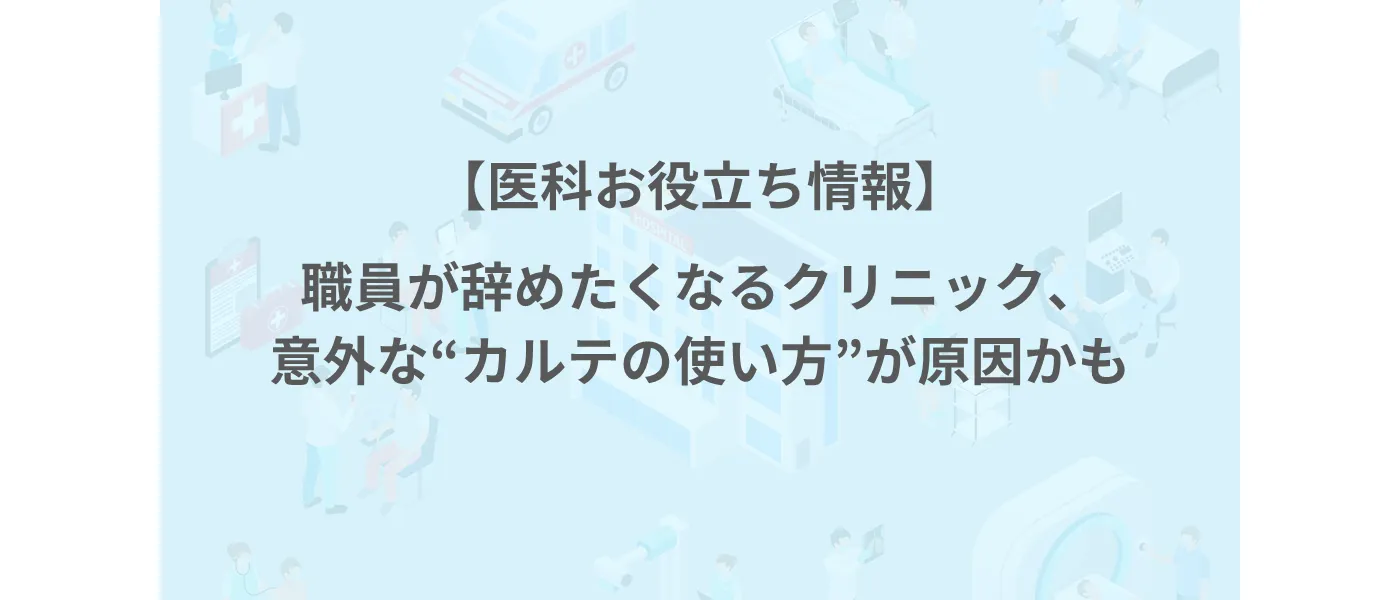
- “カルテ疲れ”が招くスタッフ離職のメカニズム
- よくある落とし穴①:業務フローに合わないテンプレート
- よくある落とし穴②:過剰な必須項目と入力ストレス
- よくある落とし穴③:更新頻度ゼロの運用マニュアル
- 改善策:現場目線での“最適化プロセス”
- まとめ:定着する職場は“使いやすさ”から
看護師として現場に携わるなかで、スタッフが「もう辞めたい」と嘆くクリニックには共通する「カルテ疲れ」の構図があると痛感してきました。 電子カルテは本来、業務効率を高める頼もしい味方ですが、設定や運用を誤ると「入力ストレス製造マシン」へと姿を変え、離職の引き金となる恐れがあります。 ここではスタッフ離職を招くカルテ運用の落とし穴を解説し、明日から実践できる最適化プロセスをご提案します。
📝 \スタッフが辞めないクリニックには理由がある/
電子カルテ導入に必要なのは、機能比較ではなく“現場定着”の視点でした。
✔ 入力のムダ・属人化の排除 ✔ 現場と経営の両立 ✔ 離職を防ぐ仕組み化
📥 今すぐDLして、定着する仕組みをチェック!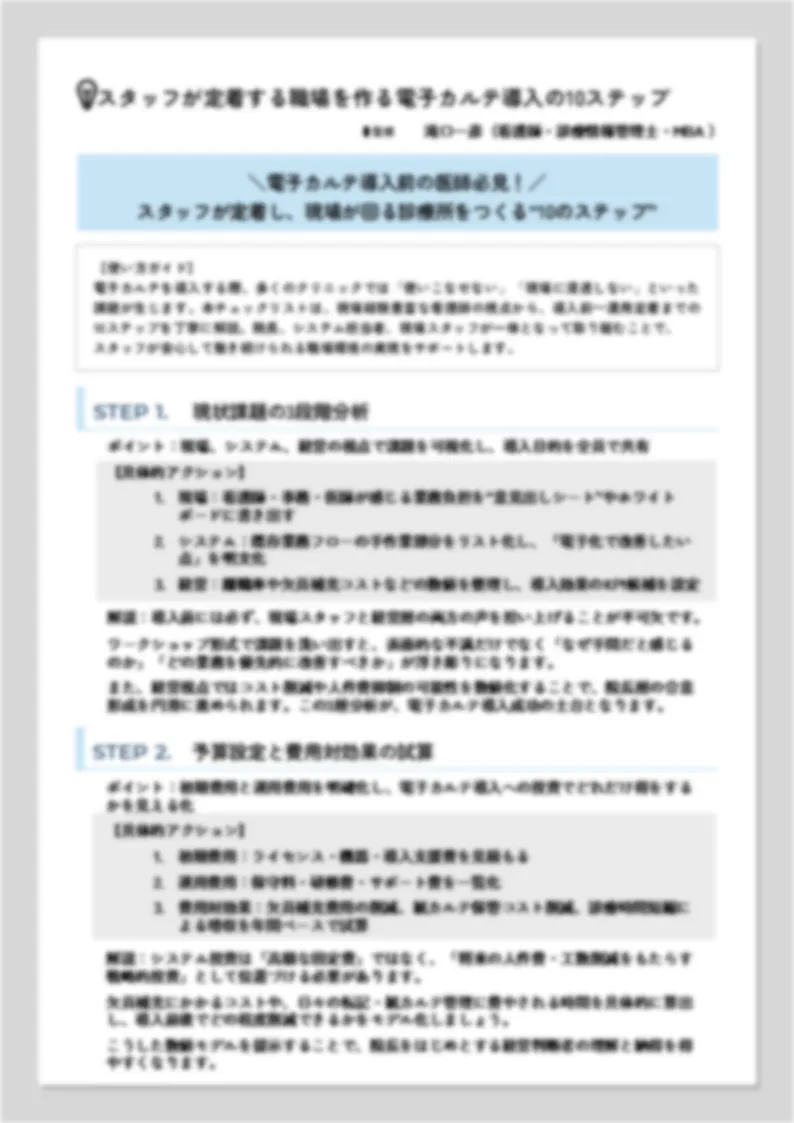
“カルテ疲れ”が招くスタッフ離職のメカニズム
1. 電子カルテが「残業の温床」になる瞬間
1-1. 端末待ちで生じる「入力待機ストレス」
クリニックに設置された電子カルテ端末がわずか2台しかないとします。
午前診のピーク時、受付スタッフが入力を終えたデータを確認しようとすると、端末がすでに使用中。
順番待ちが発生し、患者さんの診療時間後にまとめて入力作業を行うことになってしまいます。
例:看護師Aさんは午前中に6件の入力を溜め込み、診療終了直後から延々と入力開始。
結果、定時退勤は叶わず、毎日1~2時間の残業が常態化。
この「入力待ち」が累積すると、スタッフは「診療後もキーボードとにらめっこ」という生活リズムとなり、ワークライフバランスが崩壊します。
1-2. 会計締めのボトルネックが引き起こすプレッシャー
外来診療では、「電子カルテに必要情報がすべて入力されていないとレセプト会計処理が締められない」という仕様になっている場合が多いです。
たとえば、処置記録やバイタルデータの未入力があると、自動的に会計ボタンがグレーアウトして先に進めないことがあります。
例:午前診終了間際、医療事務Bさんは「入力必須」を知らせる赤いアラート表示が次々と出る画面と対峙。
患者さんは待ち続け、スタッフは「まだ終わらない」という申し訳なさと焦りで高速入力を強いられます。
この状況は「入力→会計→次の患者」という一連の流れを断ち切り、患者さんの待ち時間増を招くと同時に、スタッフに精神的なプレッシャーを与えます。
1-3. デジタルスキル格差が生む“疲れと不安”
世代や職歴によって、PC操作やタッチパネルへの慣れには大きな差があることがあり、特に開院当初から紙カルテ運用に慣れ親しんだベテラン看護師や事務スタッフは、次のようなストレスを抱えやすい傾向があります。
「クリックする場所がわからず手が止まる」→ 同僚にサポートを求めるが、ピーク時には誰も余裕がない
「マウス操作中に誤って別画面を閉じてしまい、一から入力し直し」→ エラーに対する恐怖心が募る
結果として、デジタルスキルに自信のある若手と比べ、ベテランほど「電子カルテは面倒」「自分には向かない」と感じがちです。
この心理的負荷は、日々のストレス蓄積と相まって離職意向を高める大きな要因となる可能性があります。
2. ストレスが“磁場”となり、人が辞めていく
- 心理的負荷→職場空気の悪化
入力遅延やミスへの叱責が増えると、スタッフの間に「カルテ恐怖症」が広がり、職場の雰囲気がピリつきます。
クリニックスタッフの離職理由には「精神的にきつい」が上位に挙がることが言われています。 - 医療安全リスクの連鎖
入力急かしによる誤記載は、医療事故やレセプト返戻を招き、再入力・再対応という負のループを形成します。 - 離職コストの直撃
看護師・医療事務の補充には採用広告費、教育コスト、患者対応品質低下の機会損失などが重くのしかかります。
結果的に経営を圧迫し、残ったスタッフの負担がさらに増すというスパイラルが生まれます。
よくある落とし穴①:業務フローに合わないテンプレート
1. 「万能テンプレート」は現場を苦しめる
電子カルテのデフォルトテンプレートは、あくまで一般的設定です。
業務実態に合わない項目が多いほど、スタッフは「とりあえず全部埋める」作業に追われます。
- 診療科特有の不要項目:小児科でFBS(空腹時血糖)入力必須など
- 重複入力:問診→SOAP→看護記録に同内容を転記
- 検索性低下:本当に必要な情報がノイズに埋もれ、探し物時間が増加
2. 最適化できないシステム設定
クラウド型でもカスタマイズの自由度が低い製品を選ぶと、「テンプレートの断捨離」ができないことがあります。
結果、スタッフは“使わない項目”を毎回スキップする追加操作を強いられます。
3. 改善のポイント
- タスク別テンプレート
バイタル・処置・問診など作業ごとに最小限の入力画面を作成 - プルダウン/定型文活用
手書きフリー入力より確実・高速で、誤入力防止にも効果的
役割別ビュー
医師・看護師・事務で必須項目を分け、操作迷子を防ぐ
よくある落とし穴②:過剰な必須項目と入力ストレス
1. 必須項目“過多”がもたらす3重苦
|
問題 |
スタッフ負担 |
医療安全 |
経営インパクト |
|
必須チェック過多 |
患者1人につき3分の余計な入力時間 |
チェックボックス疲労で重要項目を見落とし |
1日20人で60分の残業増 |
|
長すぎる文章入力 |
大量のタイピングで疲労が蓄積 |
誤字・脱字で診療情報が不正確に |
再入力指示で二度手間が発生 |
|
次々に現れる警告画面 |
一つの処理に何度もクリックが必要 |
"またか"という慣れで重要警告を無視 |
ヒヤリハット事例発生の可能性が増加 |
2. スタッフ心理に及ぼす影響
「全部必須」→「急いで入力」→「間違えたら訂正不可」→「改ざん扱い怖い」→「入力遅れ残業」ループが続くと、離職意向が急上昇します。
3. 解決のヒント
- アラートの優先度設定:禁忌薬・アレルギーなど生命危険に直結するもの以外は“弱アラート”へ
- 二段階必須:「診察前まで入力必須」「会計前まで入力必須」に分割し、時間的余裕を確保
- 音声入力+テンプレート:AI音声入力でタイピングを最小化し、クリック数も半減
“誰でも使える”電子カルテは、定着と業務安定の土台です。

✔ ORCAとの連動で日常業務がスムーズに
✔ 誰でも迷わず使える直感的なUI設計
✔ 導入後も、専任担当が操作定着をしっかり支援
📩 今すぐ相談する(デモ申し込み・料金など)
よくある落とし穴③:更新頻度ゼロの運用マニュアル
1. “石版マニュアル”症候群
紙ベースで分厚いマニュアルが棚の奥に眠り、誰も開かない──そんな現場では、自己流運用が横行し、入力ミスが常態化します。
- 属人化:先輩から口頭で教わるため、解釈がバラバラ
- バージョン不整合:システムアップデートにマニュアルが追いつかない
- 学習コスト増:新人が“暗黙知”を覚えるまで半年かかる
2. マニュアル未整備が生むリスク
履歴修正方法を知らずに直接上書き→改ざんとみなされるケースがあります。
これは医療訴訟リスクを高め、同時にスタッフ精神的負荷を増幅させます。
3. 生きたマニュアル運用のコツ
- オンライン化:Googleドキュメントで最新版を共有、検索機能で即参照可
- 動画+GIF:1分動画やGIFで操作手順を視覚化し、“読む苦痛”を軽減
- 改訂サイクル:四半期に1回、システム更新内容を反映しPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善のサイクル)を回す
改善策:現場目線での“最適化プロセス”
本文を記入してください
簡易ワークショップの進め方
簡易ワークショップの進め方
- 30分ミニ付箋セッション
- 患者導線図をホワイトボードに描き、入力タイミングで色別付箋を貼る
- 「ムダ」「二度手間」「わからない」を色分けすると課題が一目瞭然。
- 3段階仕分け
- ①今すぐ削除 ②後で改善 ③継続 に分類
- 付箋を動かしながら合意形成を図ることで、抵抗感を最小化
- アクションプラン化
- 改善項目を“だれが・なにを・いつまでに”でToDoリスト化
|
フェーズ |
内容 |
担当 |
期間 |
|
Plan |
課題設定・目標値(入力時間▲20%など) |
院長+リーダー |
Kickoff後1週間 |
|
Do |
テンプレート改修・教育実施 |
アンバサダー |
〜1ヶ月 |
|
Check |
ログ分析・スタッフアンケート |
アンバサダー |
月次 |
|
Action |
マニュアル更新・再教育 |
各メンバー |
四半期 |
- ログ活用:入力時間・エラー件数を自動集計し、効果を数値化
- アンケート:5段階評価+自由記述で操作感を可視化し、改善点を抽出
まとめ:定着する職場は“使いやすさ”から
カルテ運用は一見「システムの話」ですが、実際にはスタッフの働きやすさ=定着率に直結する極めて人間的なテーマです。
- 業務フローと合わないテンプレート → 「入力地獄」
- 過剰必須項目 → 「ミスと残業」
- 化石化したマニュアル → 「自己流カオス」
この三重苦を解消するには、現場目線のテンプレート最適化+軽量入力+PDCAを回す仕組みづくりがカギとなります。
電子カルテは設定次第で「スタッフ満足向上装置」に早変わりします。
まずは付箋1枚から。
サンシステムでは、カルテ導入の設計からサポートしています。
お気軽にご相談ください。
本文は実務経験と公開資料をもとに執筆し、個人情報保護のため事例は一部加工しています。
| まずは導入準備を整理したい方へ スタッフが定着する電子カルテ導入の10ステップ 📥 無料で資料をダウンロードする 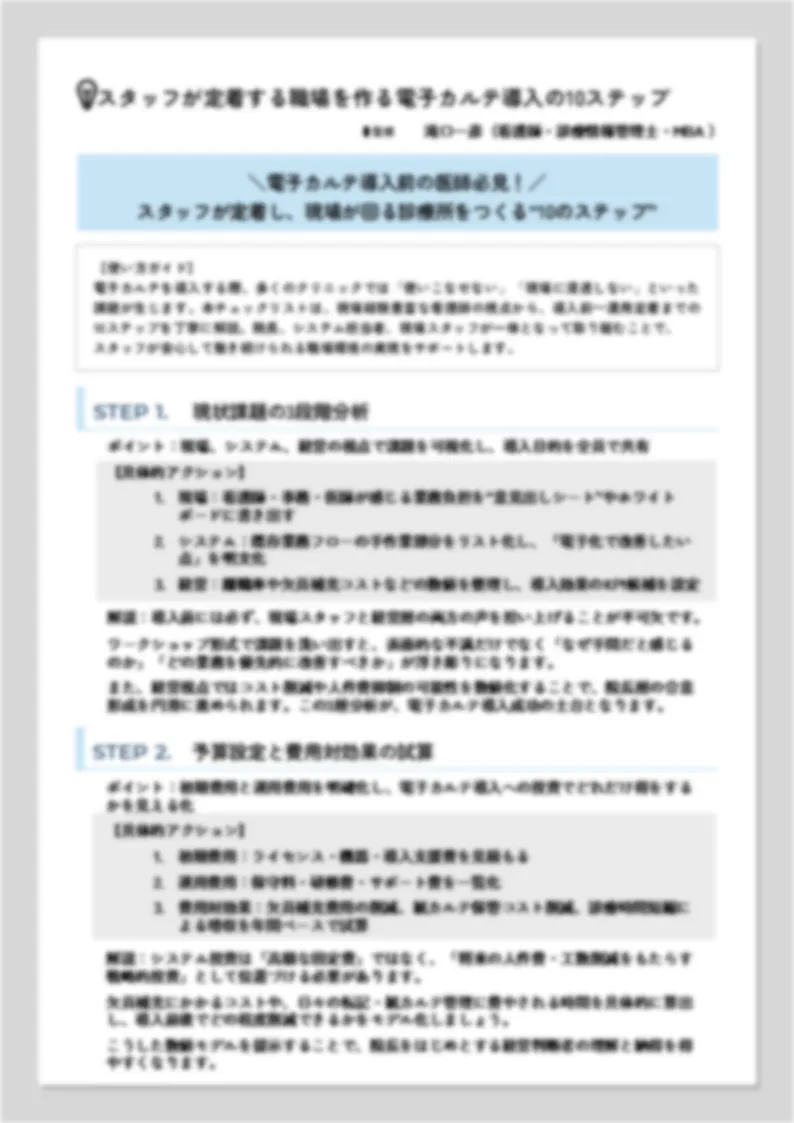 |
相談・比較したい方はこちら
【デモ】Zebra for Cloud-Karteの画面や使い勝手を体感

📩 今すぐ電子カルテ デモを申し込む
著者紹介
著者:滝口 一彦
看護師・診療情報管理士・MBA。医療現場での実務経験と経営視点をあわせ持つ医療系ライター。
大学病院・クリニックでの現場経験を活かし、電子カルテや業務効率化、スタッフ定着など、医療現場のリアルな課題に寄り添った記事執筆を得意とする。
noteでの執筆実績は300本以上。専門用語をやさしく解説し、現場目線と経営目線の両立を意識したコンテンツ制作を行う。
医療機関の現場力向上と、患者満足度・スタッフ満足度の両立を目指し、現場の声とデータに基づく提案を続けている。
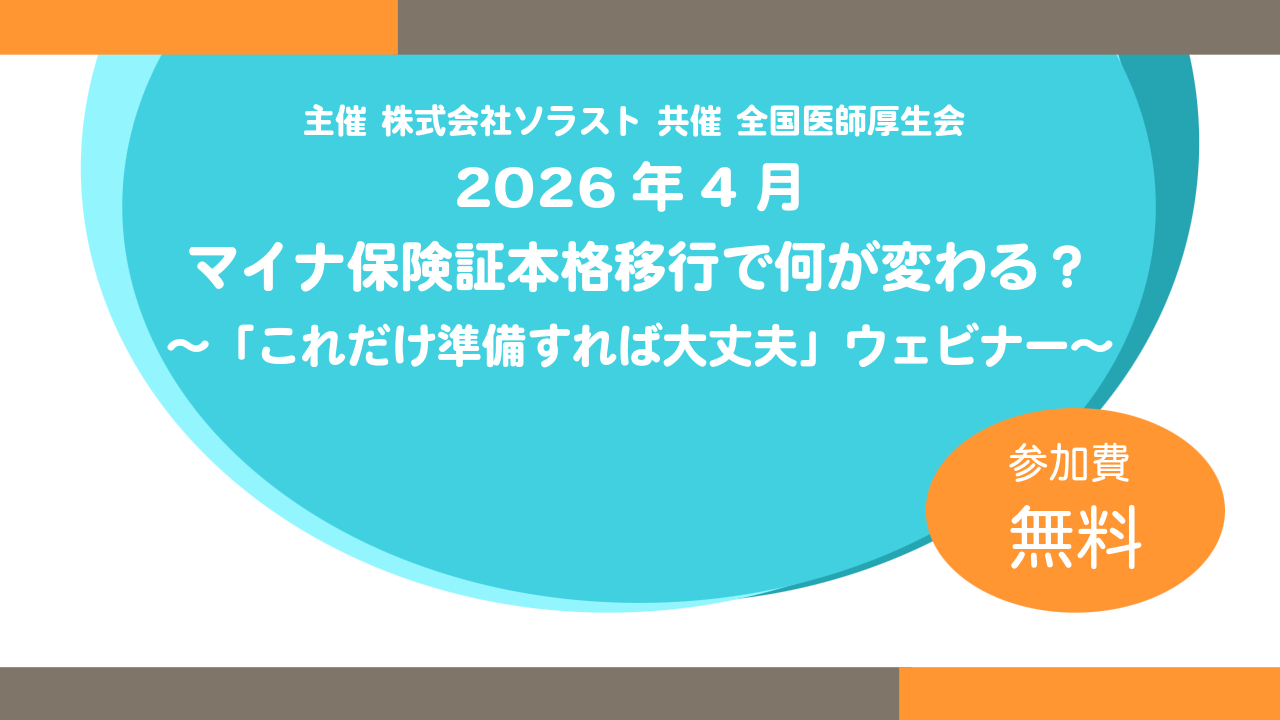
.pptx (1).webp)